| 偍偟側偑偒 | 丒恎嬤側偲偙傠偱帺慠娤嶡 丒偪傚偭偲偱偐偗偰帺慠娤嶡 丒NACS-J乮擔杮帺慠曐岇嫤夛乯娭楢偺帺慠娤嶡 |
 |
丂侽俀擭偺丄栰妶島嵗偱偺帺慠娤嶡傪偒偭偐偗偵(嵿)擔杮帺慠曐岇嫤夛偵夛堳搊榐傪偄偨偟傑偟偨丅丂埲棃丄彮側偐傜偢傾僇僨儈僢僋側曽岦傊曽恓揮姺偟偮偮偁傞乮丠乯偠偢丅偱偛偞偄傑偡乮偆偦両乯丅丂島嵗傪棧傟丄側偐側偐傂偲傝偱妶摦偡傞偺傕擄偟偄偙偲傕偁傝丄夛曬傗傜巗偺峀曬傗傜傪僠僃僢僋偟偰傂偲傝偱傕嶲壛偱偒傞僀儀儞僩傪偝偑偟偰偍傝傑偟偰乧丅丂偱偒傞偩偗丄帺慠娤嶡夛偵傕婄偩偟偨偄偲巚偭偰傑偡丅
俀侽侽俇丏俀丏侾侾乣侾俀丂帺慠娤嶡巜摫堳慡崙戝夛丂崅旜偺怷傢偔傢偔價儗僢僕
   |
丂帺慠娤嶡巜摫堳偺慡崙戝夛偲偄偆偙偲偱丄悢偊偰戞俈夞偲偄偆偙偲偱偟偨丅丂夛応偑崅旜偲偄偆偙偲偱丄偐偮偰抦偭偨傞揑側晹暘傕偁傝傑偟偰丄梋桾偺摦偒傪偟偰偟傑偄傑偄偟偨乮徫乯丅丂庴晅屻拫怘傪偲傝丄慡懱夛丅丂側傫偲偄偭偰傕報徾偵巆偭偨偺偼暯嬒憸偱傕偺傪岅傞偲偄偆偙偲丅丂幁傪椺偵庢傝丄屄懱偵拝栚偟偰偦偺堦惗傪捛偄偐偗偨僨乕僞偼峫偊偝偣傜傟傞傕偺偑偁傝傑偟偨丅丂乽偵傫偘傫乿偵抲偒姺偊偰峫偊傞偲丄偮偄偮偄暯嬒憸傪捛偄偐偗偰偟傑偆丄摉偰偼傔偰偟傑偆帺暘偑偄偨傝偟偰乧丅丂暘壢夛侾偼乽晛媦乿偵嶲壛偟偨偺偱偡偑丄偳偆傕慖戰偵幐攕偟偨傛偆偱偡丅丂媍榑偼惙傝忋偑偭偨偺偱偡偑丄帺慠娤嶡巜摫堳偺梴惉屻偺妶摦忬嫷偺捛愓暘愅偆傫偸傫丄帒奿傪偆傫偸傫乧丄嵟弶偺儃僞儞傪妡偗堘偊偨懚嵼偺傛偆偱嫃怱抧埆偐偭偨偭偡乮娋乯丅丂巜摫堳偼帒奿偠傖側偄傛偭偰偠偢丅偼嫵傢偭偨偮傕傝偩偭偨偟丄娤嶡夛偼僇僞僠偠傖側偔丄乽偄偮偱傕偳偙偱傕偩傟偲偱傕乿丄傂偲傝偩偭偰偱偒傞偟丄帺慠傪庣傞妶摦偼娤嶡夛埲奜偵傕偨偔偝傫偁傞偭偰巚偭偰偄傞傂偲側偺偱丅丂偙偺媍榑偩偲丄偠偢丅偼帒奿曉忋慻偱偡偹丅 丂怘帠屻丄暘壢夛俀偼乽傑偪偯偔傝乿丅丂乽傑偪乿偺側偐偺娤嶡偺榖偐偲姩堘偄偟偰偨傒偨偄丅丂傕偭偲傾僇僨儈僢僋側榖偱偟偨丅丂崸恊夛丄榖恠偒側偄偲偙傠傕偁傝偮偮丄庒姳撣傒夁偓偺孹岦傕偁傝偮偮乧乮徫乯丅 丂梻挬丄憗挬娤嶡夛偼憵偺傆傞側偐丄擔偺弌傪尒傑偟偨丅丂傑偁丄枅擔尒偰傞傫偱偡偑乮徫乯丅丂偨偩丄奨拞偲堘偭偰栘乆偑怓偯偄偰備偔偝傑偼側偐側偐僗僥僉側岝宨偱偟偨偹丅丂暘壢夛曬崘偑偁傝丄慡懱夛偱偼儅僱僕儊儞僩偺婱廳側榖傪暦偗傑偟偨丅丂偡偖偵偱傕怑応偱墳梡偱偒傞側偭偰丄昁巰偱儊儌偲傝傑偟偨傕傫丅丂倂俙俶俿俽丂偲丂俶俤俤俢俽丂偺暘愅側傫偐丄偪傚偭偲孈傝壓偘偰傒偨偄側偁丅丅丅 丂偭偲偄偆偄偙偲偱丄廂妌偲徚壔晄椙偑敿暘敿暘偺尋廋夛偲側傝傑偟偨丅丂偍偭偒側慻怐偺擄偟偝傪夵傔偰抦偭偨傛偆側婥傕偡傞偟丄擟堄抍懱偑擭悢傪宱偰備偔偲偩傫偩傫偲曄傢偭偰備偔偝傑傕尒偊偨傛偆側婥傕偡傞偟丅丂偦傟偧傟偵妛傃偮偮丄帺暘偺側偐偺杮幙偵岦偗偰傾僾儘乕僠傪懕偗偰備偔偭偰偙偲側偺偐側偁丄側傫偰丄彮偟偒傟偄側寢榑晅偗偱偄偐偑偱偟傚偆偐丅丅丅 |
俀侽侽俆丏俈丏侾俈乣侾俉丂儕傾儖僱僀僠儍乕僉儍儞僾丂孮攏導棙崻孲怴帯懞
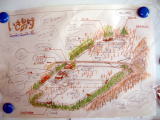     |
丂悢偊偰戞7夞偵側傞偺偩偦偆偱偡丅丂婰壇傪偨偳傞偲丄俀侽侽係擭偺妋偐丄弔偲廐傪寚惾偟偰偄傞偺偩偲巚傢傟傑偡丅丂帺恎俆夞栚偺嶲壛偲側傝傑偡偑丄摨偠応強偱傑偨傑偨堘偭偨帺慠偲偄偔偮傕弌憳偄傑偟偨丅 丂僔僑僩偵捛傢傟偨廡枛丄敋悋偁偗偱怴姴慄偵旘傃忔傝傑偟偨丅丂俀奒寶偰俵俙倃偼丄侾帪娫偲彮乆偱忋栄崅尨傑偱塣傫偱偔傟傑偡丅丂嵟嬤丄撦峴棙梡偑懡偐偭偨忋墇慄曽柺丄偁傞堄枴暼偵側傝傑偡偹丅丂墂偱尰抧僗僞僢僼偲崌棳丄崱夞偼僼傽儈儕乕偱偺嶲壛偺曽傕懡偔丄偵偓傗偐側晽忣偱偝偭偦偔偄偒傕偺懞傊岦偐偄傑偡丅丂搤偵朘傟偨偲偒偲堘偄丄廃埻偼偡偭偐傝錗偵暍傢傟偰偄傑偟偨丅丂愥偺婫愡偭偰丄偁傞堄枴堏摦偼妝側偺偐傕偟傟側偄側偁偲巚偄偮偮丄栚報偺儌儈偺栘偁偨傝傪娤嶡丅丂椺偺孎偝傫偺捾偁偲偁偨傝偱丄僙儞僒乕僇儊儔偵偼偟偭偐傝偦偺屼巔傕斺業偝傟偨偲偐丅丂摴楬偐傜傢偢偐俁侽儊乕僩儖傎偳擖偭偨偁偨傝偩偲偄偆偺偵両丂偪傚偭偲僆僪儘僉偱偡傛偹偊丅 丂拫怘傪偲傝丄愒扟椦摴傊丅丂拝幚偵恑傓曵棊抧傪捠夁偟偰丄僟儉梊掕抧偩偭偨偲偙傠傑偱丄椦摴増偄傪娤嶡丅丂崱夞偼儕僗偺帇揰偱偺娤嶡偲偄偆偙偲偱丄層搷側偳偺儕僗偺偛抷憱偵婥傪攝傝側偑傜乧丅丂搑拞丄僽僫偺幚乮丠乯偲偄偆僔儘儌僲傪弶傔偰娽偵偟丄偪傚偭偲姶寖丅丂懠偵傕僒儚僔僨偲僀僰僔僨傪偮傇偝偵斾妑娤嶡偟偨傝丄儕僗偑抲偒朰傟偨偱偁傠偆偲偙傠偐傜丄夎悂偄偨層搷偺偍偐偁偝傫傪扵偟偨傝丅丂憡曄傢傜偢丄敪尒偼恠偒傑偣傫丅 丂廻偵栠偭偰擖梺丄梉怘丅丂崱夞偺栭僾儘偼僫僀僩僴僀僋丅丂尭懍偟偰恑傓幵拞偐傜尒傞奜偺晽宨偼丄僥乕儅僷乕僋偺傾僩儔僋僔儑儞傪渇渋偲偝偣傑偡丅丂拫娫曕偗偽傕偺偺俆暘偺曑憰楬傕丄巕嫙偨偪偵偼側偐側偐庤偛傢偄傕偺偩偭偨偐傕偟傟傑偣傫偹丅丂愒偄儔僀僩偼偝偭偦偔崱擭偺壞偵帋偟偰傒傛偆偲巚偄傑偡偑丅 丂梻挬丄憗挬娤嶡夛偼揷傫傏偺廃傝丅丂僇僄儖丄僩儞儃丄僙儈側偳偵壛偊丄摴楬偺岦偙偆偺曽傪墶抐偡傞丄璩偺戉楍偲偱偔傢偟偨傝丄挬偐傜側偐側偐偺廂妌両挬怘屻偵曎摉傪僓僢僋偵偮傔丄僶僗偱忋墇崙嫬傊丅丂嶰崙尃尰偱俁僌儖乕僾偵暘偐傟丄擏懱攈乮丠乯偠偢丅偼栘摴傪忋偑傝偍壴敤傊丅丂嶐擭偼僣儕僈僱僯儞僕儞傗僋儖儅儐儕偑栚棫偭偰偄偨偲偙傠偑丄堦柺僯僢僐僂僉僗僎偺戝孮棊両丂傑偝偵僷儞僼儗僢僩偦偺傕偺偺丄愨岲偺僞僀儈儞僌偱偺嶳峴偲側傝傑偟偨丅丂杮摉偵丄偍壴敤偲偄偆偵傆偝傢偟偄偡偽傜偟偄岝宨偵悓偄偟傟傑偟偨丅 丂廻偵栠偭偰堦晽楥梺傃偰丄嵞傃忋栄崅尨傑偱僶僗偱堏摦丄夝嶶偲側傝傑偟偨丅丂攡塉偑柧偗偨偙偺擔丄梊曬偼偁傑傝傛偔側偐偭偨偺偱偡偑丄寢壥偲偟偰偼俀擔偲傕崀傜傟偢丅丂偨偩丄夝嶶屻丄儂乕儉偱怴姴慄傪懸偭偰偄傞娫偵丄奜偼嫮楏側梉棫偵廝傢傟偰偄傑偟偨偹丅丂傗偼傝乧乮徫乯丅仼撪椫庴偗偱偡両丂崱夞傕丄嬝擏捝偲堷偒姺偊偵乮両乯丄怷偺塰梴傪偨偭傉傝偄偨偩偄偰棃傑偟偨丅丂岼偱偼偳偆傗傜壞媥傒傕巒傑傞崰崌偄偩偭偨傛偆偱丄傗偼傝僼傽儈儕乕偭偰僉乕儚乕僪偼偙傟偐傜偺僉儍儞僾偱奜偣側偔側傞偺偐側丠丂妋偐偵偙偆偄偭偨廻攽峴帠偵愊嬌揑偵嶲壛偟偰傎偟偄悽戙偺傂偲偨偪偭偰乧丅丂偁傜偨傔偰帺暘偺摿庩惈乮丠乯傪奯娫尒偨傛偆偵婥傕偟側偑傜丄婣傝偺怴姴慄偼傂偨偡傜柊偭偰偍傝傑偟偨丅丂僗僞僢僼偺傒側偝傑丄崱夞傕偍旀傟條偱偛偞偄傑偟偨両  丂 丂 丂 丂 |
俀侽侽俆丏俁丏俆乣俇丂儕傾儖僱僀僠儍乕僉儍儞僾丂孮攏導棙崻孲怴帯懞
     |
丂婫愡傪偄偔偮傕旘傃墇偊偰丄愥偺愒扟僄儕傾偵嵞傃懌傪摜傒擖傟傑偟偨丅丂嶐擭偺搤僉儍儞僾偺廰懾偺巚偄弌偑傾僞儅傪偐偡傔丄憗傔偵弌敪丅丂俇帪傪夞偭偨偙傠偵娭墇楙攏傪捠夁偡傞傕丄偲偙傠偳偙傠旝柇側廰懾丅丂慜擔枹柧偵崀偭偨愥偼偡偭偐傝娭搶暯栰偄偪傔傫傪敀偔愼傔偰偍傝丄廰懾偺憢墇偟偵尒傞揷敤偼偡偭偐傝搤宨怓丅丂揤婥梊曬傪暍偡傛偆偵丄嵍庤偐傜嵎偟崬傓挬擔丅丂側傫偲側偔棳傟傕僗儉乕僘偵側偭偨偲偙傠偱丄偍栺懇偺SA壖柊乮徫乯丅丂慜夞丄悰暯埲棃丄幵偵怮戃忢旛偱偡丅丂側傫偰傗偭偰傞偲晄堄偵実懷偑柭傞丅丂搶嫗墂儂乕儉偐傜偍桿偄偺揹榖丅丂偁傟偭丠幵偱峴偔偭偰尵偄朰傟偰偨偐偟傜丠丠丠丂傑偁丄偄偄僞僀儈儞僌偺栚妎傑偟偱偟偨丅 丂楍幵慻偲忋栄崅尨偱崌棳丅丂尰抧偼愥柾條丅丂夞暅孹岦傪怣偠偰丄偄偮傕偳偍傝廻偱恎巟搙丄儅僀僋儘僶僗偵忔偭偰尰抧傊丅丂崱夞偼愥偑嶐擭傛傝懡偔丄梊掕偝傟偰偄偨彫弌枔戲乮偍偄偢傑偨偝傢乯偼婋尟偲偺敾抐偐傜丄儉僞僑戲傊曄峏丅丂妋偐偵丄嶐擭傛傝偢偄傇傫庤慜傑偱偟偐僶僗偼擖傟傑偣傫偱偟偨丅丂偝偭偦偔僗僲乕僔儏乕傪棜偄偰椦摴傪偁偑傝傑偡丅丂嶐栭偐傜崀傝懕偄偨愥偑堦柺偵崀傝愊傕傝丄懌愓偼偡偭偐傝徚偝傟偰偟傑偭偨柾條丅丂嵀愓傜偟偒傕偺傪偄偔偮偐尒偮偗傜傟傞偵偲偳傑傝傑偟偨偑丄弔傪屇傇儐僉儉僔偺弌寎偊傪庴傑偟偨丅丂揤婥傕偡偭偐傝夞暅偟丄愥尨偵栘乆偺塭偑慛傗偐偵晜偐傃忋偑偭偰偄傑偟偨丅 丂摛晠偯偔偟偺梉怘偺偁偲丄栭偺儗僋僠儍乕丄偝傜偵柉榖傪暦偔廤偄偵傕嶲壛偟丄壏愹傪悘強偵嫴傒偮偮丄岎棳丅丂偁偭丄偪側傒偵崱夞偼尒帠俇扨埵偘偭偲偱偟偨丅 丂挬娤嶡夛丅丂嶐栭偝傜側傞僆乕僶乕僞僀儉偑偁偭偨傛偆側榖傕偁傝偮偮丄傒側偝傫僴儎僆僉偱偟偨丅丂捁偺惡傪暦偒側偑傜偖傞偭偲侾帪娫庛偺嶶曕偺偁偲丄偦偺懌偱挬怘僽僢僼僃丅丂挬偐傜僇儞僪乕偺楢懕偱偟偨丅丂旤枴偟偡偓偰偮偄怘傋偡偓偓傒偩偭偨偺偼巹偱偡丄偼偄丅丂偱丄巟搙偦偙偦偙偵僶僗偱弌敪丅丂俀擔傔偼乽偄偒傕偺懞乿偲屇偽傟傞丄愒扟僾儘僕僃僋僩偺慜慄婎抧傊偍幾杺偟傑偟偨丅丂傕偲傕偲椦栰挕偺昪曓偵椬愙偟偨栘憿偺寶暔偱丄偡偱偵巊梡偝傟側偔側偭偰偄偨傕偺傪庁傝庴偗丄夵憿惔憒傪宱偰尰嵼偵帄偭偰偄傞柾條丅丂嶐擭丄榖偼暦偄偰偄傑偟偨偟丄曐岇嫤夛偺夛曬帍偱傕庢傝忋偘傜傟偰偄偨偺偱丄忣曬偼帩偭偰偄傑偟偨偑幚嵺偵峴偔偺偼弶傔偰丅丂偄偮傕峴偔愳屆壏愹傛傝偢偭偲庤慜偵偁傝丄摉弶偼傑偝偵儀乕僗偲偟偰偺棙梡傪峫偊偰偄偨傜偟偄偺偱偡偑丄傆偨傪奐偗偰傒傞偲偙傫側傾僗僼傽儖僩摴楬偭傁偨偵傕丄偙傫側偵傕偄偒傕偺偑両偭偰偙偲偱丄娤嶡偺慜慄婎抧偲側偭偰偄傞傛偆偱偡丅丂幚嵺偵僙儞僒乕僇儊儔傪妶梡偟丄僂僒僊丄僥儞丄僒儖丄僞僰僉丄側偳側偳丄偝傑偞傑側偄偒傕偺偺峴偒棃偑偁傞偙偲偑妋擣偝傟偰偍傝傑偟偨丅丂偡偭偐傝惏傟搉偭偨愥尨偵偼妋偐偵柍悢偺懌愓偑乧丅丂偲偙傠偳偙傠偵僆儈儎僎側傫偐傕乮徫乯丅丂偝傜偵丄壗杮偐偺栘偵偼偟偭偐傝孎偝傫偺捾偁偲側傫偐傕偔偭偒傝偲巆偭偰偄傞偁偨傝丄杮摉偵帺慠偺朙偐偝傪姶偠偢偵偼偄傜傟傑偣傫傛偹丅丂傢偞傢偞墱傑偱峴偐側偔偰傕丄偙傫側嬤偔偵両偭偰榖偱偡傛丅 丂拫怘傪偄偨偩偒丄廻偵栠偭偰偝傜偵傂偲偭晽楥梺傃偰丄怳傝曉傝丅丂傗偭傁傝偙偙偵棃傞偲丄乽傑偨棃傑偡両乿偭偰偙偲偽偱掲傔偔偔傞偙偲偟偐偱偒傑偣傫丅丂崱擭偼怴椢偺婫愡偵丄峴偗傞偐側偁乧丅丅丅 丂偦偆偦偆丄崱寧偺偄偪傑偄丄偳偆傗傜僩僠偱偁傞偙偲偑敾柧両丂偙傟傕廂妌偱偟偨両 |
俀侽侽係丏俈丏侾俈乣侾俉丂儕傾儖僱僀僠儍乕僉儍儞僾丂孮攏導棙崻孲怴帯懞
     |
丂係搙栚偺嶰崙偱偡丅丂嵟弶偺島廗夛偑壞偺廔傢傝丄偦偟偰廐丄搤丅丂怴椢偺僀儀儞僩偼僔僑僩偺搒崌偱寚惾偟傑偟偨偑丄壞偺擖傝岥偱丄怷偼傑偨丄堘偭偨昞忣傪尒偣偰偔傟傑偟偨丅 丂傑偢弶擔丄巜掕偝傟偨怴姴慄偱崌棳丅丂偄偮傕偳偍傝忋栄崅尨偱廻偺儅僀僋儘僶僗偵忔傝姺偊丄恎巟搙傪偟偰弌敪丅丂崱擔偼媽嶰崙奨摴傪怴妰偐傜孮攏傊栠傞偲偄偆丄嶐擭廐偲摨偠僐乕僗偱偟偨丅丂峠梩偵愼傑偭偨崰偲偼堘偄丄椢擹偄怷偵懌傪摜傒擖傟傞偲丄儅僀僫僗僀僆儞偑廩枮偟偰偄傞傛偆側丄傂傫傗傝偲偟偨嬻婥偺弌寎偊傪庴偗傑偟偨丅 丂嶰崙尃尰偐傜栘摴傪嶳捀曽柺傊忋偑傞僐乕僗偼慜夞偼捠傜側偐偭偨晹暘丅丂婫愡偑傜偐丄偲偵偐偔偨偔偝傫偺壴傪尒傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅丂昗崅傕侾係侽侽傪墇偊傞偁偨傝側偺偱丄偄傢備傞崅嶳怉暔偺椶偵娷傑傟傞傕偺傕懡偔尒傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅丂嶲壛幰偺偁偄偩偱偼偁傟偙傟柤慜傕旘傃岎偆偺偱偡偑丄椺偵傛偭偰柤慜傪妎偊傞偙偲偵幏拝傪偟側偄偠偢丅偱偁傝傑偟偨丅丂偍壴敤偱拫怘丅丂怘屻偵僾儘僌儔儉傪侾杮丄崱夞偼怓巻偵側偵偐彂偄偰傒傛偆偲偄偆婇夋偱偟偨丅丂嶳捀傪攚偵偡傞偲塃庤偵昪応偺僗僉乕応丄嵍庤偵愒忛偺嶳丅丂傑偝偵偙偙偼帺暘偺拞偺搤偲壞偺恀傫拞側傫偩側偁乧丄側傫偰僇儞僇僋傪昞尰偟偰傒偨偮傕傝側傫偱偡偑丄憡曄傢傜偢奊偺傎偆偼乧丅 丂壓傞摴偡偑傜偵傕僉儗僀側壴偑偄偔偮傕嶇偄偰偄傑偟偨丅丂廻偵栠偭偰偄偄壏愹丄偦偟偰偍偄偟偄怘帠傪偄偨偩偄偨屻丄懽擩帥偲偄偆偍帥傑偱僶僗偱弌偐偗傑偟偨丅丂拫娫庒姳塉傕崿偠傞傛偆側揤婥偩偭偨偺偱偡偑丄傃偭偔傝偡傞傎偳偺儂僞儖偺棎晳傪尒傞偙偲偑弌棃傑偟偨丅丂埫埮偱抮偵塮傞偐傜側偍偝傜側偺偐傕偟傟傑偣傫偑丄偪傚偭偲僇儞僪乕傕偺偱偟偨丅 丂梻挬丄俁侽暘傎偳廻偺嬤強傪娤嶡偟丄嵞傃愒扟椦摴傊丅丂俁寧偼彫弌枔戲偺傎偆傊擖偭偨偺偱丄偙偪傜偼傾僇僱僘儈傪尒偰埲棃偵側傞傫偱偡偹丅丂傂偲搤墇偊偰丄偲偙傠偳偙傠曵棊偑恑傫偩傝偟偰偄傞傛偆偵傕巚偊傑偟偨偑丄傗偼傝曄傢傜偢朙偐側怷偱偟偨丅丂儎儅價儖偔傫偨偪傕尦婥偱偟偨偹乮徫乯丅 丂崱夞傕丄怷偵尦婥傪傕傜偭偰婣偭偰偒偨傛偆偵巚偄傑偡丅丂捠偭偰偄傞偆偪偵丄婄側偠傒傕憹偊偰偒偨偟乮徫乯丅丂偱傕丄側偐側偐帪娫偑偲傟側偄偺傕尰幚側偺偱偡丅丂偼偄乧丅丅丅 丂  丂丂 丂丂 丂丂 丂丂 |
俀侽侽係丏俁丏侾俁乣侾係丂儕傾儖僱僀僠儍乕僉儍儞僾丂孮攏導棙崻孲怴帯懞
     |
丂偝偡傜偄偺僐僺乕儔僀僞乕丄傒偨傃尰傞両丠丂偦傫側僲儕偱偼側偄偱偡偑丄嵞傃嶰崙偺怷偵擖傝傑偟偨丅丂崱夞偼帺慠娤嶡偲僗僲乕僔儏乕偺懱尡偑儊僀儞僾儘偩偭偨偐偲巚偄傑偡丅 丂挬俇帪慜偵壠傪弌偰丄崱夞偼幵偱尰抧傊岦偐偄傑偟偨丅丂搒撪偑巚偄偺傎偐廰懾乧丅丂棤摴傪敳偗丄娭墇偵偺偭偨崰偵偼帪寁偼俉帪丅丂偟偐傕栚偵旘傃崬傫偱偔傞廰懾係俈僉儘偺僇儞僶儞乧丅丂傂傗傂傗偟側偑傜丄彊乆偵廰懾傕夝徚偟丄廤崌帪崗傎傏傄偭偨傝偵忋栄崅尨摓拝丅丂婄側偠傒偺抧尦僈僀僪偺曽偲崌棳偟丄怴姴慄偺摓拝傪懸偪傑偟偨丅丂乽崱擔偼捒偟偔惏傟偰傑偡偹乿側傫偰堄枴怺側夛榖偑杮戉摓拝傑偊偵岎傢偝傟偰偄偨偙偲偼旈枾丠丂儅僀僋儘僶僗偺屻偵廬偄丄偄偭偨傫廻傊擖傝傑偡丅丂巟搙傪惍偊丄儉僞僑戲傊丅丂朄巘壏愹傛傝壓棳偐傜榚傊擖偭偨椦摴傪恑傒傑偡丅丂偙偙偼弶傔偰偺応強偱偡偹丅丂愥傪摜傒偟傔側偑傜偝傑偞傑側嵀愓傪廍偄偮偮丄傑偨丄愥偺傾乕僩偵戣柤傪偮偗側偑傜忋棳傊丅丂偦傠偦傠拫怘億僀儞僩丄偭偲偄偆偲偙傠偱僇儌僔僇偺娊寎傪庴偗傑偟偨丅丂怘屻丄僗僲乕僔儏乕偺懱尡丄愥忋娤嶡偺僎乕儉側偳傪偟偰偄傞偆偪偵乧丄偍傗偍傗丄揤婥偑乧丅丂傗偭傁傝両丠偭偰惡偑楻傟偮偮傕椦摴傪壓傝丄愒戲僗僉乕応傊丅丂僎儗儞僨榚偺椦偵傕偨偔偝傫偺摦暔偺嵀愓傪尒偮偗丄傑偨傕堄奜側懱尡偑偱偒傑偟偨丅 丂栭偺儗僋僠儍乕丄壏愹丄岎棳偑偁偭偨偙偲偼尵偆傑偱傕側偔丄梻擔偼彫弌枔戲乮偍偄偢傑偨偝傢乯増偄偺椦摴傊丅丂栘乆偼偡偭偐傝梩傪棊偲偟丄傑偭偨偔堘偭偨宨怓偵側偭偰偄傑偟偨丅丂偝偡偑偵愥偑怺偔丄乽宩僗僥乕僔儑儞乿傗乽偼偠傑傝偺扟乿傑偱偼偨偳傝偮偗傑偣傫偱偟偨偑丄搤側偍帺慠偺朙偐偝傪姶偠偝偣偰偔傟傞怷偵嵞搙姶摦丅丅丅丂僗僲乕僔儏乕傪棜偄偰戲増偄傑偱偔偩傝丄峏偵姶摦丅丅丅丂 丂憡曄傢傜偢丄忋庤側尵梩偱偼岅傟傑偣傫偑丄乽傑偨棃傑偡両乿偦偆尵偄巆偟偰丄崱夞偺僉儍儞僾傪暵偠傑偟偨丅丂師夞偼夎悂偒偺崰偱偟傚偆偐丅丂傑偨丄堘偭偨婄傪尒偣偰偔傟傞傕偺偲婜懸偟偰偍傝傑偡丅丂傂傚傫側偙偲偐傜丄偍庤揱偄偝偣偰偄偨偩偄偨僉儍儞僾僐僺乕丄亀傒傫側偱巆偣偨乽傑傞偺傑傫傑偺帺慠乿偺拞傊丄弔偺懅悂偲杮摉偺傗偝偟偝傪扵偟偵峴偒傑偣傫偐亁偼丄堄恾揑偵嶌偭偨僐僺乕偱偼側偔丄偠偢丅偑巚偭偰偄傞偙偲偦偺傑傫傑偩偭偰偙偲偩偲巚偄傑偡丅丂偼偄丅 丂僉儍儞僾僗僞僢僼丄側傜傃偵嶲壛幰偺傒側偝傑丄崱夞傕偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅丂姶憐側偳丄惀旕偍婑偣偔偩偝偄丅丂偲偭傉傌乕偠偐傜儊僀儖儕儞僋偑偁傝傑偡偺偱両 丂乮仺僉儍儞僾偵偮偄偰偼偙偪傜乯 丂乮仺俙俲俙倄俙僾儘僕僃僋僩偵娭偟偰偼偙偪傜乯 |
俀侽侽俁丏侾侽丏侾侾乣侾俁丂儕傾儖僱僀僠儍乕僉儍儞僾丂孮攏導棙崻孲怴帯懞
     |
丂嶰崙偺怷傊傕偆堦搙両偭偲偄偆偙偲偱丄俙俲俙倄俙僾儘僕僃僋僩娭楢偱幚巤偝傟偨僉儍儞僾傊嶲壛偟偰傑偄傝傑偟偨丅丂傂偲偮偒慜傛傝傕峏偵僨傿乕僾偵丄怷偺墱傊偲擖偭偰偄偒傑偟偨丅 丂愭寧偲摨條丄怴姴慄偱忋栄崅尨丅丂廻偺儅僀僋儘偵僺僢僋傾僢僾偟偰傕傜偄丄恎巟搙傪惍偊偰傑偢弶擔偼愒扟椦摴傊丅丂搑拞傑偱偼島廗夛偱擖偭偨偲偙傠偱偡偑丄崱夞偼僟儉寶愝偑梊掕偝傟偰偄偨抧揰傑偱擖傝傑偟偨丅丂椦摴増偄偵僼傿乕儖僪僒僀儞傪廍偄側偑傜備偭偔傝俁帪娫傎偳丄搑拞傾僇僱僘儈偺恊巕偑彫偝側偑偗増偄偺偔傏傒傪憱傝夞傞巔偵偱偔傢偟傑偟偨丅丂抧尦偱娤嶡傪懕偗偰偄傞僈僀僪偺曽傕弶傔偰尒傞岝宨偲偺偙偲偱丄旕忢偵岾塣偩偭偨偲巚偄傑偡丅丂幨恀傪嶣傞偺傕朰傟偰偟偽偟尒擖偭偰偟傑偄傑偟偨丅丂 丂俀擔栚偼椬偺彫弌枔戲乮偍偄偢傑偨偝傢乯増偄偺椦摴傪擖傝傑偟偨丅丂偝傑偞傑側庬椶偺怉暔丄偦偟偰偨偔偝傫偺僼傿乕儖僪僒僀儞偵偮偄偮偄懌傕巭傑傝偑偪偵側傝側偑傜丄栺俁僉儘愭偺捠徧宩僗僥乕僔儑儞傑偱丅丂帋偟偵應偭偰傒偨傜偍偲側俈恖偱傛偆傗偔傂偲傑傢傝偡傞宩偺戝栘傪嬄偓側偑傜偺拫怘丅丂媫幬柺傪戲偵岦偐偭偰壓傝偨偲偙傠偵偁傞丄偸偨応傕偁傞扟偵擖傝僀僞儎僇僄僨偺戝栘傪尒偮偗偨傝丄偐偮偰恉扽椦偲偟偰巊傢傟偰偄偨偙偲傪帵偡扽梣偺偁偲傪偺偧偄偨傝丄偨偔偝傫偺怴慛側懱尡傪偟傑偟偨丅僈僀僪偺曽傕懠偺嶲壛幰偺曽傕帺慠偵徻偟偄曽偑偽偐傝偱丄偝傑偞傑側夝愢偑偁偪偙偪偱旘傃岎偄丄傑偨丄堘偭偨妏搙偺乽栚偑奐偄偨乿傛偆側婥偑偟偰偄傑偡丅 丂嵟廔擔偼忋墇崙嫬偺僩儞僱儖傪偔偖傝丄怴妰懁偐傜嶰崙摶傪墇偊朄巘戲偵壓傝傞僐乕僗丅揤婥壓傝嶁偺梊曬捠傝丄僩儞僱儖傪敳偗傞偲偦偙偼乧柖偺拞丅丂偟偐偟丄婫愡偼柧傜偐偵傂偲偮搤偵嬤偯偄偰偄傞宨怓偺拞丄怓偯偒偑崱傂偲偮偲尵偄側偑傜傕偒傟偄偵愼傑偭偨峠梩偺拞傪備偭偔傝偲曕偒傑偟偨丅丂崙摴傑偱壓傝偰偒偨偲偙傠偱杮奿揑偵崀傝巒傔丄塉懳嶔傪偟偰朄巘戲傪壓傝傑偟偨丅丂僽僫偺戝栘偵姶寖偟偮偮妸傝傗偡偄懌尦傪妋偐傔側偑傜朄巘壏愹傑偱丅丂楢媥偺塉偺偣偄偐丄偦偆偲偆崿傒偁偭偰偼偄傑偟偨偑丄偣偭偐偔側偺偱壏愹偵傕偮偐傝丄寎偊偺僶僗偱廻偵栠傝傑偟偨丅丂廻偱拫怘偺偁偲丄傑偲傔傪偟偰夝嶶偟傑偟偨丅 丂忋庤側尵梩偑尒偮偐傜側偄偟丄忋庤偵昞尰偡傞偙偲偱偱偒偰偄側偄偺偱偡偑丄帺暘偵偲偭偰偼乽帺慠偺朙偐側怷乿偭偰偄偆傕偺偑偳傫側傕偺側偺偐丄夵傔偰巚偄抦偭偨傛偆側婥傕偟偰偄傑偡丅丂傕偪傠傫丄徻偟偄曽偨偪偵夝愢偟偰傕傜偄側偑傜夞傞偙偲偑偱偒偨偐傜側偍峏側偺偐傕偟傟傑偣傫丅丂偨偩丄側偤偐嫽暠偟偰偄傞帺暘偑偙偙偵偄傞偺傕帠幚偱偡丅丂弌偐偗傞慜擔偵嫽暠偟偰柊傟側偔側傞巕嫙偲媡偱丄婣偭偰偒偰偐傜旀傟偰怮擖偭偨偁偲傕柇偵柊傝偺愺偝傪挬偵側偭偰姶偠偰偄傑偡丅丂傕偆彮偟丄偄傗傕偭偲傕偭偲丄偙偺怷偲娭傢偭偰偄偨偄偲棪捈側巚偄偱丄儗億乕僩傪暵偠偨偄偲巚偄傑偡丅 乮仺僉儍儞僾偵偮偄偰偼偙偪傜乧嬤偔傾僪儗僗曄傢傝偦偆側婥偑偡傞側偀乯 乮仺俙俲俙倄俙僾儘僕僃僋僩偵娭偟偰偼偙偪傜乯 |
俀侽侽俁丏俋丏侾俁乣侾俆丂帺慠娤嶡巜摫堳島廗夛丂孮攏導棙崻孲怴帯懞丂愒扟愳乮愳屆壏愹廃曈乯
    |
丂廐偺栰妶戞堦抏両偲偄偆偙偲偱丄俁夞栚偺墳曞偵偟偰傛偆傗偔嶲壛偺愗晞傪庤偵擖傟偨島廗夛傊峴偭偰嶲傝傑偟偨丅丂暦偔偲偙傠偵傛傞偲侾侽夞埲忋奜傟偰偄傞恖傕崱夞偺嶲壛幰偵偼偄傑偟偨偺偱丄寢峔塣偑偄偄傎偆側偺偐傕丅丂挬俆帪戜偺揹幵偵傑偝偵旘傃忔傝丄俈帪偺怴姴慄偵妸傝崬傒丄忋栄崅尨墂傊丅丂傎偳側偔寎偊偺儅僀僋儘僶僗偑摓拝偟丄島廗夛偺巒傑傝偱偡丅丂 丂丂丂丂丂乮仺島廗夛偺偍偍偞偭傁側僗働僕儏乕儖偼偙偪傜丂 丂傑偢岦偐偭偨愭偼怴帯懞擾懞娐嫬夵慞僙儞僞乕丅丂偙偙偱庴晅丄奐島幃傪嵪傑偣偰偝偭偦偔幚廗僼傿乕儖僪傊丅丂偄偮傕偺島廗夛偱偼廻攽丒島媊丒幚廗傪傂偲傑偲傔偵峴偭偰偄傞傛偆偱丄堏摦傪娷傓働乕僗偼傑傟偲偺偙偲丅丂僶僗偱侾俆暘傎偳偱愳屆壏愹偵摓拝丅丂嫶偺忋偐傜偺僗働僢僠偺偁偲丄嶲壛幰係俉柤傪俁偮偺斍偵暘偗偰幚廗嘆丅丂妋偐偵僼傿乕儖僪偼堘偆偗傟偳丄晛抜尒姷傟偰偄傞偺偲摨偠傛偆側怷偺晽宨偑偡偭偐傝堘偆傕偺偵尒偊傞偔傜偄丄徴寕揑側幚廗偱偟偨丅丂帇揰傪曄偊偰尒傞偲偄偆偙偲偺戝愗偝傪夵傔偰幚姶丄摢傪椻傗偟側偑傜丠偺拫怘偺偁偲丄壨尨偱帺屓徯夘傪峴偄丄島媊夛応傊堏摦丅 丂梉曽偺島媊丄偦傟傕俁帪娫両丂挬傕憗偐偭偨偟丄偍偦傜偔乧丄偲巚偄側偑傜僲乕僩PC棫偪忋偘偰島媊偵朷傒傑偟偨丅丂偲偙傠偑偙偺島媊偺撪梕傕丄帺暘偵偼愗傝岥偑怴慛偱傑偝偵乽偁偭両乿偄偆娫偺俁帪娫偱偟偨丅 丂丂丂丂丂乮仺島媊嘆偺儊儌偼偙偪傜丂 丂島廗夛俀擔傔丅丂偨偭傉傝怮偨偼偢偑懡彮僇儔僟偺廳偝傪姶偠偮偮愳屆壏愹傊堏摦丅丂屵慜偼乽抧堟偺帺慠傪棟夝偟傛偆乿偲偄偆僥乕儅偱怉暔丒摦暔丒抧幙偺俁恖偺島巘傪弰偭偰偺幚廗丅丂屵屻偼乽帺慠娤嶡夛偺僥乕儅偝偑偟乿偲偄偆偙偲偱丄俁恖偺帺慠娤嶡巜摫堳偑偦傟偧傟偺愗傝岥偱僥乕儅偺僞僱傪搳偘偐偗偰偔傟傑偟偨丅丂側傞傎偳両偲巚偄偮偮丄偡偱偵摢偺拞偼僆乕僶乕僼儘乕偓傒丅丂娽傪敀崟偝偣側偑傜丄島媊夛応傊偲堏摦偡傞偺偱偁傝傑偟偨丅 丂梉曽偺島媊偼嵞傃俁帪娫丅丂島巘偺曽偑敀攏懞棊憅嵼廧偲偺榖偱傑偢傃偭偔傝丅丂側偵偣妛惗帪戙偐傜侾侽悢擭捠偄搢偟偨丄尵偭偰傒傟偽僕儌僩偺榖丅丂偮偄偮偄暦偒擖偭偰偟傑偄傑偟偨丅丂偦偟偰丄帺慠娤嶡夛偺儕僗僋儅僱乕僕儊儞僩偺榖側偳偼晛抜偺栰妶偲廳側傞晹暘偑偐側傝偁傞傢偗偱乧丅丂偙偺擔傕俁帪娫偼乽偁偭両乿偲偄偆娫偵夁偓偨偺偱偟偨丅 丂丂丂丂丂乮仺島媊嘇偺儊儌偼偙偪傜丂 丂偝偁丄嵟廔擔偱偡丅丂島廗夛偺巇忋偘偼俆暘娫偺儈僯娤嶡夛傪幚嵺偵傗偭偰傒傞偲偄偆帋楙偑懸偭偰偄傑偡丅丂慡懱揑側愢柧偺偁偲丄屵慜拞偱帺暘側傝偺僥乕儅傪愝掕偟丄僾儘僢僩傪峫偊丄僾儗僛儞偺巇曽傪楙傞傢偗偱偡丅丂怘帠傪偟側偑傜傕偁傟偙傟巚偄傪弰傜偣偮偮丄傗偼傝帪娫偼偡偖偵夁偓傞傕偺偱乧丅丂孈傝壓偘偰偄偔偆偪偵摉弶丄摢偵偁偭偨僥乕儅偐傜旝柇偵僘儗偰偄偒偮偮丄嵟廔揑偵偼偄偄姶偠偵巇忋偑偭偨偐偲巚偄傑偡偑丄偳偆偱偟傚偆偐偹丠 丂丂丂丂丂乮仺幚廗儗億乕僩偼傑偲傔偰偙偪傜丂 丂僗働僕儏乕儖偺娭學偱丄偍偟傑偄偑僶僞僶僞偵側偭偰偟傑偄傑偟偨偑丄杮摉偵撪梕偺偙乕偄丄俁擔娫偱偟偨丅丂懡暘丄偙偺僐乕僼儞丄暥柺偐傜揱傢傝傑偡傛偹乮徫乯丅 丂丂丂丂丂乮帺慠娤嶡巜摫堳島廗夛偵嫽枴傪帩偭偨曽偼偙偪傜丂 |
| 俀侽侽俆丏係丏俀俁乣俀係丂嶳嵷仏栰憪椏棟偺偮偳偄(娤嶡曇) 丂偼偄丄擇晹峔惉偺敿暘偱偡丅丂椏棟偺榖偼栰奜悊帠偺儁乕僕傪偛棗偔偩偝偄丅丂挬俉帪偵偳傫偖傝嶳憫傑偊偵廤崌偟丄俀戜偺幵偵暘忔丄嵟弶偵朘傟偨偺偼偐偮偰傗偳傝偓偺僉儍儞僾応傊捠偭偰偄偨偲偒偵捠偭偰偄偨棤摴両丂僑儖僼応偺偡偖墶偱偁傝傑偟偨丅丂偠偢丅偵傕傢偐傞乮両乯僲價儖偵巒傑傝丄儈僣僶乮栰惗偱傕偁傞傫偱偡偹乯丄抧崠偺姌偺奧偲偄偆垽徧乮丠乯傪傕偮僉儔儞僜僂側偳傪揈傒傑偟偨丅丂応強傪堏摦偟偰導柉偺怷丅丂椦摴傪偁偑傝側偑傜傑偩彫偝側儓儌僊傪揈傒丄壴偼偼偠傔偰尒傞僴僫僀僇僟傪揈傒傑偟偨丅丂偝偡偑偵栚偺撏偔斖埻偺僞儔偺夎偼傎傏偲傜傟偰偍傝乮徫乯丄傛偭傐偳庤偺撏偐側偄傛偆側偲偙傠偺傕偺偼偡偭偐傝戝偒偔怢傃偰偍傝傑偟偨丅丂偍暊偺帪寁偑拫傪巜偟偨偺偱丄儀乕僗偵栠傝丄拫怘丅丂屵屻偐傜庤暘偗偟偰椏棟傊撍擖偱偡丅 丂梻擔丄傑偁丄庒姳嶐栭偺儌僲偑巆偭偰偄傞曽傕偄傜偭偟傖偄傑偟偨偑乮偠偢丅偼廡偺旀傟偑弌偰憗乆偵寕捑乯丄挬怘偺偁偲導棫恅栰價僕僞乕僙儞僞乕庡嵜偺扵捁夛偵嶲壛偟傑偟偨丅丂憃娽嬀偺儗儞僞儖傪庁傝偰丄悈柍愳偧偄傪偖傞傝俀帪娫庛偺僐乕僗偱偟偨偑丄惓捈傃偭偔傝偡傞偔傜偄捁偑尒傜傟傑偟偨両丂偄偒側傝塣椙偔僆僆儖儕偲弌偔傢偟丄椦偺拞偱偼僐僎儔傕偟偭偐傝憃娽嬀偺拞偵曔傜偊傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅丂傎偐偵傕僈價僠儑僂偑偛偦偛偦曕偔巔偲丄偦偺巔偲偼堦晽曄傢偭偨偒傟偄側偝偊偢傝丄側偳側偳丅偨偭偨俀帪娫庛偱侾侽悢庬椶偺捁偲懳柺偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅丂怉暔傕堄奜偲朙晉偱丄偄偔偮傕弔傪姶偠傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅丂偄傗偼傗丄恎嬤側偲偙傠偵傕偢偄傇傫偲偄偄偲偙傠偑偨偔偝傫偁偭偨傫偱偡偹丅丂夵傔偰丄僕儌僩垽偵栚妎傔偨傛偆側婥偑偟傑偟偨乮徫乯丅 |
 丂 丂 丂 丂 丂 丂  丂 丂 丂 丂 丂 丂 |
    |
俀侽侽係丏俈丏俁侾丂孮攏導棙崻孲怴帯懞 丂尵傢偢偲抦傟偨丄帺慠曐岇嫤夛丄AKAYA僾儘僕僃僋僩偺抧偱偛偞偄傑偡丅丂巜摫堳島廗夛傗儕傾儖僱僀僠儍乕僉儍儞僾偱壗搙傕懌傪塣傫偱偄傞偲偙傠偱偡偑丄崱夞丄愒忛偵擖傞慜偵丄偪傚偄偲俁帪娫偽偐傝曕偄偰嶲傝傑偟偨丅丂乮偭偰丄UP偑堎條偵抶偔偰偛傔傫側偝偄両乯 丂崱夞偼愳屆偐傜彫弌枔戲乮偍偄偢傑偨偝傢乯増偄偺椦摴傪擖傝傑偟偨丅丂拝偄偨帪偵偼偁偄偵偔偺塉柾條傕丄幵偱堦柊傝偟偰偄傞偆偪偵偡偭偐傝忋偑傝丄塤娫偵偼惵嬻傕丅丂嶐擭廐偵朘傟偨丄捠徧乽僇僣儔僗僥乕僔儑儞乿丄偦偟偰乽偼偠傑傝偺扟乿偺壞偺條巕傪偳偆偟偰傕尒偨偐偭偨丄偭偰偄偆偺偑儂儞僱偱偡丅丂偙傟傑偱戝惃偱曕偄偰偄偨椦摴傪傂偲傝傏偭偪偱忋偭偰偄傞偲丄偙傟傑偱偲偼堘偭偨姶妎傪妎偊傑偟偨偹丅丂側傫偲昞尰偟偰傛偄偺偐偼傢偐傜側偄偺偱偡偑丅丂偦偟偰丄乽偼偠傑傝偺扟乿丄崱夞偼偟偭偐傝幨恀偵廂傔偰偒傑偟偨丅丂慜夞偼埑搢偝傟偰僔儍僢僞乕傪愗傞偺傕朰傟偰偄偨傫偱偡偗偳偹丅丂偱傕丄偁偺暤埻婥丄偳偆尒偰傕揱傢傝傑偣傫偹丅丂傗偼傝帺慠偼乽僫儅乿偑偄偪偽傫偱偡傛両丂偭偰丄偁傝偒偨傝偺寢榑丠丠丠  丂丂 丂丂 丂丂 丂丂 |
  |
俀侽侽係丏俈丏係乣俉丂杒奀摴 丂崱擭偼杒奀摴偱傂偲傝帺慠娤嶡夛傪傗偭偰偄傑偟偨乮徫乯丅丂偲偼尵偭偰傕丄愮嵨偼擖傝偺彫扢丄僯僙僐丄敓娰偺堏摦偩偭偨偺偱丄偦傟傎偳帺慠枮媔偭偰僇儞僕偱偼側偐偭偨偱偡丅丂偱傕丄側傫偲尵偭偰傕丄僯儏乕僗偱棳傟傞搒撪俁俇搙両偭偰偄偆揤婥梊曬偵丄愴乆嫲乆偲偟側偑傜傕偮偐偺娫偺夣揔惗妶偱偟偨丅 丂柧傜偐側怉惗偺堘偄偲丄婫愡姶偺堘偄傪偟傒偠傒偲挱傔偰偄傑偟偨丅丂偱傕丄側傫偲尵偭偰傕敤偵嶇偄偨枮奐偺壴丄恀偭敀偩偭偨傝丄傎偺偐側敄巼偩偭偨傝丅丂峀戝側敤偵峀偑傞晽宨偼丄婜娫尷掕偺僗僌儗儌僲偩偭偨偲巚偄傑偡丅丂壗偺壴偩偐暘偐傝傑偡偐丠丂夝摎偼俉寧偺偄偪傑偄偱両 |
俀侽侽俁丏俇丏俀乣俇丂壂撽 |
丂壂撽偱傂偲傝帺慠娤嶡夛傪傗偭偰偄傑偟偨乮徫乯丂僩僢僾僯儏乕僗偵傕彂偒傑偟偨偑丄撿偺搰偺怉暔丄偲偭偰傕嫽枴怺偄傕偺偑偁傝傑偟偨丅丂崱傑偱偙偆偄偭偨帇揰偱尒偰偄側偐偭偨偐傜側偍偝傜側偺偐傕偟傟傑偣傫偑丄傕偺偺尒曽丠偡偙偟偼傾僇僨儈僢僋偵側偭偰偒偨偺偐偟傜丠 丂偝偰丄堦斣嫽枴傪傂偄偨偺偑幨恀偺朠檧栘乮傎偆偍偆傏偔丄朠檧庽偲傕偄偆傜偟偄乯偱偡丅丂撨攅巗栶強慜偵傕奨楬庽偲偟偰怉偊傜傟偰偄傑偟偨丅側偤嫽枴傪傂偄偨偐偲偄偆偲丄悢擭慜偵僒僀僷儞傊峴偭偨偲偒偵尒偨撿梞嶗偵帡偰偄傞乮屆偄榖偵側傝傑偡偑丄儘儞僶働偺僆乕僾僯儞僌偵偱偰偒偨傗偮偱偡両乯偲巚偭偨偐傜偱偡丅丂偟偐乕偟丄僶僗偺塣揮庤偝傫偵暦偄偰傒傞偲丄暿偠傖側偄偐丄偲偺曉帠丅丂偲偙傠偑婣偭偰偒偰偐傜僱僢僩偱挷傋偰傒傞偲丄撿梞嶗偲屇偽傟傞栘偼壗庬椶偐偁傞傜偟偔丄偦偟偰偦偟偰偠偢丅偑尒偨僒僀僷儞偺撿梞嶗偼側傫偲側傫偲朠檧栘偩偭偨偙偲偑敾柧両丂偪傚偭偲旲崅乆偵側偭偰偟傑偄傑偟偨乮徫乯丂丂嶲峫仺傗偟偺幚戝妛 丂傕偆傂偲偮栚偵偮偄偨傕偺丄偦傟偼汃抾搷乮偒傚偆偪偔偲偆乯偱偟偨丅丂墶昹偱傕晛捠偵尒傞壴偑壂撽偱傕偁偪偙偪偱尒傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅丂埲慜丄峀搰偱尨敋懱尡偺榖傪暦偄偨拞偵丄汃抾搷偺愒偄壴傪尒傞偲偁偺弸偄壞偲擱偊偨嬻偺怓傪巚偄弌偡乧丄偲偄偆傕偺偑偁傝丄偠偢丅偺拞偱偼偳偆偟偰傕愴憟偲愗傝棧偣側偔側偭偰偟傑偭偨壴傪丄壂撽偺愴愓偱傑偨尒傞丅丂側傫偲傕偄偊側偄憐偄偑傛偓偭偨弖娫偱偟偨丅 |
俀侽侽俁丏俆丏侾侾丂愮梩導丂徍榓偺怷
丂崱夞偼俆寧枛偵嶲壛婓朷傪偟偰偄偨帺慠娤嶡巜摫堳尋廋夛偺拪慖偵奜傟偰偟傑偭偨偺偱丄傑偁丄偦偺夛応偺條巕傪尒偵偄偔僀儈傕偁偭偰嶲壛偟偰偒傑偟偨丅僥乕儅偼乽弔偺僩儞儃扵偟乿偲偄偆偙偲偱丄偳偆傗傜愮梩導帺慠娤嶡巜摫堳嫤媍夛偲偄偆抍懱偑徍榓偺怷偱枅寧奐嵜偟偰偄傞掕婜揑側帺慠娤嶡夛偩偭偨傛偆偱偡丅乮夛応偱抦傝傑偟偨両乯
丂傑偢偼僼傿乕儖僪丄杮摉偵戝偒側岞墍偱偟偨丅斾妑揑惍旛偝傟偨恖岺偺岞墍晹暘偲丄庣傜傟偰偄傞乮丠乯帺慠偺晹暘偲偑揔搙偵偁偭偰乧丄偲偼偄偭偰傕慡晹傪傑傢傝偒傞偙偲偼偱偒側偐偭偨偺偱側傫偲傕偄偊傑偣傫偑乧丅偱丄僥乕儅偺僩儞儃側傫偱偡偑丄惓捈丄偙偺帪婜偵丠偭偰巚偄側偑傜僼傿乕儖僪傪曕偄偰偄傞偲丄寢峔偄傞傕傫偱偡偹両弔堦斣偺僔僆儎僩儞儃偲僔僆僇儔僩儞儃偺嬫暿傪偟偭偐傝曌嫮偟偰偒傑偟偨丅偁偲丄僸僈僔僇儚僩儞儃偺嶻棏丄側傢偽傝傪挘傞偺偱嬤偯偄偰傕摝偘側偄偺偱娫嬤偱尒傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偙傟偐傜偺婫愡丄庬椶傕偳傫偳傫憹偊偰偄偔傛偆偱偡偺偱丄晛抜偐傜栚慄傪偁偘偰曕偄偰傒傛偆偐側乧側傫偰峫偊側偑傜婣偭偰偒傑偟偨丅
俀侽侽係丏俇丏侾俆丂丂嶰宬墍
丂傎偨傞傉傠偠偉偔偲丄戞侾抏偵偄偭偰偒傑偟偨丅乮戞俀抏偼偁傞偺偐丠乯拫娫偑偭偮傝僔僑僩偟偰丄傎傏僿僩僿僩忬懺偱尰拝丅拫偐傜僺僋僯僢僋婥暘偟傖傟偙傫偱偄傞愭敪戉偲崌棳丅偍抮偺岋偲媃傟側偑傜丄傂偨偡傜埫偔側傞偺傪懸偮丅傑偁丄俀廡枛俇擔娫尷掕偺栭娫奐墍偺偨傔偐丄傂偲偑憹偊傞憹偊傞乧丅妋幚偵寀偺侾侽攞偼傂偲偑偄偨偹乮徫乯丅娐嫬嫵堢偑嫨偽傟傞側偐丄偳偆偟偰傕偙偆側偭偰偟傑偆偺偑斶偟偄丅傂偲偩偐傝偵側偭偰傕偄偄傛両偱傕丄晽忣傪妝偟傓僉儌僠偼朰傟側偄偱偄偰梸偟偄側偁丅偒偭偲丄寀偼儊僀儚僋偟偰偨偲巚偆側丅娫堘偄側偔乮敋乯丅
俀侽侽係丏俀丏侾俆丂丂偔傠偑偹
丂偊偭偲乧丄僨傿儗僋僞乕偺帋尡偑偁偭偨傕偺偱丄偪傚偄偲憗傔偵摓拝偟偰丄棤嶳偺弔偺夎惗偊傪扵偟偵峴偒傑偟偨丅擔拞丄斾妑揑抔偐偩偭偨偣偄偐丄捁偑偄偭傁偄弌偰傑偟偨偹丅僉儌僠偺栤戣偐傕偟傟傑偣傫偑丄弔両偭偰姶偠偺柭偒曽偱偟偨丅偁偲偼乧丄帺暘偺僇儊儔偵儅僋儘偑偮偄偰偄傞偺傪攦偭偰侾擭宱偭偰傛偆傗偔婥偯偄偰丄壴尒偲偐偟偰傑偟偨乮徫乯丅偁偭丄俁寧偺偄偪傑偄偼偪傖傫偲僎僢僩偟偰傑偡偺偱丄偍妝偟傒偵丅丅丅丂仺壴尒偼偙偪傜
| 俀侽侽俁丏侾侾丏侾俇 丂丂丂丂丂丂丂丂丂偔傠偑偹     |
丂偼偄丄偦偆偄偆傢偗偱乽榬復僨價儏乕乿壥偨偟傑偟偨乮徫乯丅嶲壛幰偵偼傢偐傞丠棤榖宯偺榖偱捲偭偰傒傑偡丅 丂慜擔崀傞偼偢偺塉偑旝柇偵彮側偔丄梊憐奜偵惏傟娫傕弌偨傝偟偰偼偭偒傝偟側偄揤婥丅梊曬偱偼栭敿偐傜崀傝偩偡塉偑屵慜拞傑偱巆傞柾條丅偁偝丄俆帪敿偵偼婲偒側偗傟偽娫偵崌傢側偄偺偱丄憗偔怮傛偆偲巚偄偒傗丄枹柧偐傜崀傝弌偟偨塉偺寖偟偝偵壗搙傕僇乕僥儞傪傔偔傞丅寢嬊帪寁偺恓偑偰偭傌傫傪傑傢偭偨偁偨傝偱傛偆傗偔廇怮丅偦傫側傢偗偱偁偭偲尵偆娫偵傔偞傑偟偺壒丅僇乕僥儞傪傔偔傞丅旘傃崬傫偱偒偨偺偼傑偩徠柧偺巆傞奨暲傒偵丄偡偭偒傝偲悷傒搉偭偨嬻両偍傕傢偢幨恀傪嶣偭偰偟傑偄傑偟偨乮徫乯丅 丂揹幵俁楬慄偵僶僗傪忔傝宲偄偱尰抧傑偱侾帪娫敿庛丅嬼慠墂偱傕偆傂偲傝偵傾僔僗僞儞僩偝傫偲崌棳丅島嵗摨婜偺廋椆偱敿擭怳傝偺嵞夛丅僶僗偺拞偱嬤嫷偲忣曬偺岎姺傪偡傞丅梊掕帪崗傛傝憗傔偵摓拝丅扴摉僗僞僢僼偼傑偩摓拝偟偰偄側偄丅偙偺寗偵抶偄丠挬怘丅偍偭偮偗僗僞僢僼摓拝丅島巘傕摓拝丅崱夞偺島巘偼偠偢丅偑愒扟偱島廗夛傪庴偗偨偲偒偺扴摉偩偭偨曽丅偝偭偦偔僼傿乕儖僪傪嵞妋擣偟側偑傜忣曬岎姺丅島嵗偺棳傟偲梊掕偟偰偄偨僾儘僌儔儉傪偐傒崌傢偣傞寉傔偺儈乕僥傿儞僌傪偟側偑傜丄帺慠娤嶡偺忣曬傕偄偔偮偐傕傜偆丅栺俁侽暘偺嶶嶔偱偄偪偵偪傇傫偺僱僞偁傢偣傪偟丄摨帪偵傑偨愗傝岥丄巋寖傪媧廂偡傞丅偙偺帪揰偱偡偱偵乽偁偁丄崱擔偼棃偰傛偐偭偨乿傕乕偳偵撍擖両 丂偝偰丄奐夛幃傪廔偊偝偭偦偔島嵗偺僗僞乕僩丅偣偭偐偔偩偐傜偍栺懇偺怷偺偡偗偭偪偼島廗夛偱傕嵟弶偵峴偆僾儘僌儔儉丅崱夞偼偠偢丅偺儕僋僄僗僩偱擖傟偰傕傜偄傑偟偨丅戝偒偔尒傞丄尒傞仺娤傞丄偵偼幚偼嵟揔側僾儘偩偲巚偄傑偡丅偆傑偄傊偨偠傖側偔丄壗偑尒偊偨偐丄暦偙偊偨偐丄姶偠偨偐偑僟僀僕側傫偱偡丅懕偄偰壠栦傪巊偭偰怉暔偝偑偟丅帺慠偲傂偲偲偺娭傢傝傪挿偄帪娫幉偺側偐偱尒傑偟偨丅偙偙偱傕堄奜側傕偺偲偄偔偮傕弌埀偄丄僫僀僔儑偱偨偔偝傫儊儌偲傝傑偟偨丅懕偄偰摦暔偵側偭偰偐偔傟傫傏丅恖娫偵尒偮偐傜側偄傛偆偵摦暔偨偪偼怷偺拞偐傜偳傫側僉儌僠偱尒偰偄傞偐丄彮偟偼偦傫側婥暘傪枴傢偆偙偲偑偱偒偨偱偟傚偆偐丠偙偺偁偲棤嶳傪傂偲傑傢傝偡傞梊掕偩偭偨偺偱偡偑丄帪娫偑側偔側傝丄偣偭偐偔摦暔偺僉儌僠偵側偭偨偺偱丄僿價丄彫捁丄僋儅乧偵側偭偰偙偺僼傿乕儖僪偱侾擭屻傑偱惗偒巆傟傞偐傪峫偊傑偟偨丅 丂拫怘屻丄僌儖乕僾偵暘偐傟偰娤嶡夛偺僥乕儅扵偟傪偟偰傕傜偄傑偟偨丅島廗夛偺巇忋偘偵傗傞僾儘偱偡偑丄梊憐偳偍傝乮丠乯僾儘嶌傝偵偼偄偪偠偮偺挿傾儕偺姶偑偁傝傑偟偨丅偝偡偑島嵗惗丄堦斒偺島廗夛偱偼偁傫側偵傕嬅偭偨娤嶡夛偼奐偗傑偣傫傛丅傑偁丄恖悢偺娭學傕偁傝傑偡偗偳偹丅栰妶惗偺愗傝岥偱俈偮偺僾儘僌儔儉偑揥奐偝傟傑偟偨丅俈偮傔偺僾儘揥奐拞偵乽嵟屻偪傚偭偲帪娫偁傞偐傜丄俷俛偺僾儘偱偁傟傗傝傑偣傫丠乿偲偝偝傗偐傟乮仼偙傟偑懪偪崌傢偣俁昩偺拞恎偱偡乯丄乽偠偢丅偺帺慠娤嶡夛乿傕嵟屻偵偔偭偮偗偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅 丂嵟屻偵壆撪偵擖偭偰傑偲傔傪偟傑偟偨丅廔傢傞崰偵偼偲偭傉傝偲擔傕曢傟偰乧丅帩偭偰偄傞忣曬傪搳偘崬傫偱丄偲埶棅偝傟偰偄偨偼偢側偺偵丄庢傝崬傫偩忣曬偺傎偆偑懡偐偭偨傛偆側乧丄偦傫側偄偪偵偪偱偟偨丅嶲壛幰偺傒側偝傑丄僗僞僢僼丄島巘偺傒側傒側偝傑偵姶幱偭両両両 |
| 俀侽侽俁丏侾侾丏侾俁 丂丂丂丂丂幚摜丂偔傠偑偹   |
丂乽偄偮偱傕偳偙偱傕偩傟偲偱傕乿偑帺慠曐岇嫤夛偺偄偆帺慠娤嶡夛偱偡丅棟孅偱偼傢偐偭偰偄傞偗傟偳丄偠傖偁丄幚嵺偳偆側偺傛丠偭偰偄偆偲丄乧側僇儞僕偱偟偨丅崱傑偱丄杮摉偵帺慠偺朙偐側怷偵擖偭偰帺慠傪枮媔偡傞帺慠娤嶡傪偟偰偄傑偟偨丅偱傕丄弌偐偗偰偄偔偺偱偼側偔丄恎嬤側帺慠傪娤嶡偟偰丄恎嬤側帺慠偺曐岇偐傜巒傔傛偆丄偲偄偆偺偑杮棃偺庯巪側傢偗偱丅 丂偦傫側憐偄傪偄偩偒偮偮丄島嵗偺帺慠娤嶡偱巊梡偡傞僼傿乕儖僪偺幚摜偵峴偭偰偒傑偟偨丅偄傢備傞愄夰偐偟偄棦嶳偺偍傕偐偘偑巆傞晹暘偲拫側偍埫偄抾傗傇偲乧丅嵟弶偼僉僣僀側偁偲姶偠偨傝傕偟傑偟偨丅偱傕偺傫傃傝曕偄偰偄傞偆偪偵丄寢峔偄傠偄傠側傕偺偑尒偊偰偒傑偟偨丅幚嵺丄娤嶡偺懳徾偲側傞偐偳偆偐偼暿偵偟偰丄偠偢丅偺怗妎偵怗傟傞傕偺偑偄偔偮偐尒偮偐傝傑偟偨丅乽偙傫側偲偙傠偵傕偙傫側傕偺偑両乿偲偐乽側傫偐偐傢偄偄傕偺尒偮偗偰摼偟偨婥暘両乿偲偐丄偦偺掱搙側傫偱偡偗偳偹丅偱傕丄懡暘偦傟偑偄偪偽傫僟僀僕側姶妎側偺偱偼側偄偐偲巚偭偰傒偨傝傕偡傞偺偱偡丅摿暿側傕偺丄捒偟偄傕偺傪尒偮偗傞偺偑栚揑偱偼側偄偐傜丄帺暘偺姶惈偵怗傟傞傕偺偑偄偔偮尒偮偐傞偐丄偦傟偑妝偟傒側偺偱偼側偄偐偲丄偦傫側憐偄傪傕偭偰婣偭偰傑偄傝傑偟偨丅廡枛丄偳傟偩偗僼僅儘乕偱偒傞偐偼傢偐傝傑偣傫偑丄偠偢丅側傝偺僱僞傪傕偭偰丄椢偺榬復姫偄偰嶲忋偟傑偡乮徫乯丅 |